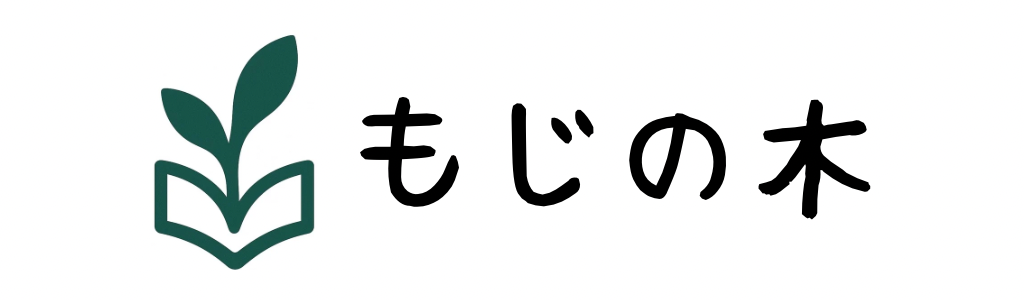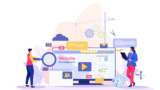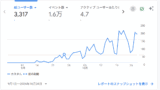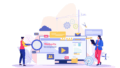「せっかく上位を取ったのに、アップデートで全部落ちた…」
──この悩み、毎年のように聞こえてきます。
でも、本当に強いサイトはアルゴリズムに振り回されません。
なぜなら、「一次情報」と「体験」を軸にしているからです。

この記事で理解できること
✅ なぜアップデートで順位が落ちるのか
✅ 変動に強い記事の本質
✅ 「一次情報×体験」の実装方法
✅ もじの木がアップデートに強い理由
✅ 長期資産になる記事設計
なぜ変動に弱いのか:従来のSEOの大きな誤り
多くの企業が「アップデートで吹き飛ぶ」ということは、そのサイト設計に根本的な問題があるということです。


えっ…リライトとAIと競合分析は、みんなやってることじゃ…
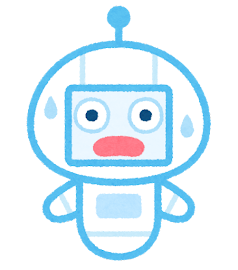
そっや!だからみんなアップデートで一緒に落ちるんや!Googleは「独自性」を求めてるんや!
変動に強い記事の本質:「一次情報×体験」が全て

では、何があれば「変動に強い」記事になるのか。
答えは「他に代替できない、その企業固有の情報」です。
一次情報とは:自分たちだけが語れる情報
これらは、他のサイトでは絶対に書けません。なぜなら、その企業にしかない情報だからです。
たとえば「SEOライティング」というキーワードなら、一般的な情報は誰が書いても同じです。
でも「弊社で100社以上のSEOライティング支援をした結果、『●●』という法則が見つかった」という情報は、その企業にしかありません。
体験とは:血の通ったストーリー
「顧客A社は最初、キーワード選定に失敗していました。でも、こういうアプローチに変えたら、わずか3ヶ月で流入が3倍になりました。理由は…」
このように「誰が・どこで・何を・どう感じたか」という流れで書くだけで、記事が一気に息づきます。
Googleは最近「E-E-A-T」を強化しています。つまり、機械的な情報より「人間味のあるナレッジ」を評価しているということです。
実装の型:「一次情報×体験」を自然に組み込む

では、実際にどうやって組み込むか。
パターン①:導入部に現場エピソードを添える
従来の記事
「SEOライティングとは、Google検索で上位に表示されるための文章技法です。多くの企業が…」
一次情報を入れた記事
「先日、食品メーカーのマーケ担当者から『SEOライティングで成果が出ません』と相談されました。調べてみると、キーワードを詰め込むだけで『読者が何を求めているか』が見えていなかったんです。ここから設計を変えたら、わずか2ヶ月で流入が2倍に。その経験から、本当に機能するSEOライティングの秘訣が見えてきました。」
どちらが「読みたい」と思いますか?
パターン②:本文に「なぜそうなったのか」の理由を組み込む
従来の記事
「SEOライティングのコツは、キーワードを含める、見出しを工夫する、本文を1000文字以上にする、といわれています。」
体験を入れた記事
「実際に100社以上の事例を見てきて気づいたのは『キーワードだけ詰め込んでも上位は取れない』ということ。なぜか。Googleは『このキーワードを検索した人は、本当は何を求めているのか』を理解している企業を評価するからです。逆にいえば、その『読者の本当の欲求』を満たす記事を書けば、キーワードは自然に含まれるんです。」
実体験と理由がセットになると、記事に説得力が生まれます。
パターン③:CTAに実績・ストーリーの延長を使う
従来の記事
「SEOライティングは、弊社にお任せください。質の高い記事を提供します。」
体験を入れた記事
「同じように『読者が本当に求めている欲求』を軸に記事設計を変えた企業は、アップデートでも順位が落ちていません。むしろ、変動のたびに競合との差が広がっている状態です。あなたも、このアプローチで一度試してみませんか?」
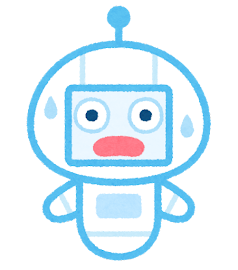
ほら!実績があると、CTAも信頼度が違う!「買ってください」より「一緒に成功しませんか」になるんや!
よくある勘違い
企業にとってのメリット:「アップデートに強い資産」

もじの木だからできること
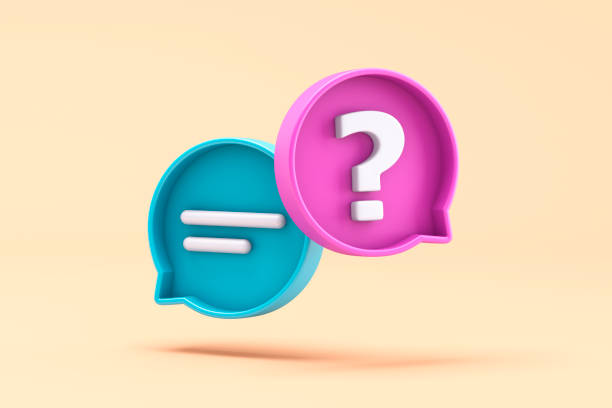
「一次情報×体験」は重要だけど、普通は時間がかかります。
事例をヒアリングして、構成を練り直して、ストーリーを組み込んで…これは、通常、1記事に1週間以上かかります。
でも、もじの木は違います。
結論:「アルゴリズム対応」ではなく「本質設計」
Googleアップデートに強いサイトと弱いサイトの差は、そもそも設計にあります。
量産よりも「何を伝えるか」
文字数よりも「誰が語るか」
リライトよりも「体験があるか」
もじの木は、型の力を使って「速さ+本質」の両立を実現します。
だから、フェーズ①で積み上げた記事が、そのままフェーズ②③での資産になり、アップデートで落ちることなく、ずっと集客し続けるんです。
「アルゴリズムに左右されない土台」を、今のうちに作っておきませんか?
まずは1本、一次情報ベースの記事を出してみてください。その先に見える「変動に強いサイト」の形が、必ず見えてきます。
SEO記事制作を外注するなら「もじの木」
リサーチ・構成・執筆・装飾・WordPress入稿まですべてワンストップ対応。
7,000文字の記事を最短1営業日(通常3営業日)で納品。
文字単価1.5円で、高速×高品質なSEO記事を実現しています。
今なら初回限定で、7,000文字相当1本を無料で執筆。
「まずはクオリティを見てから依頼したい」という方に最適です。