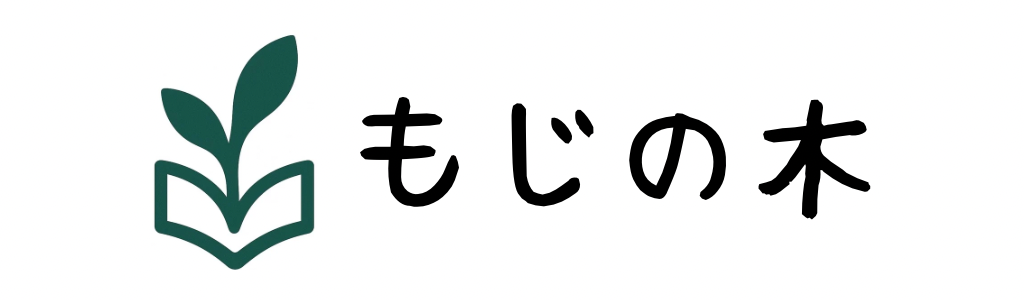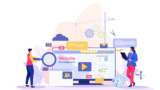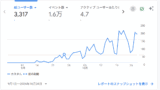「SEO記事を月に10本、外注してるのに…商談がほとんど増えない」
この悩み、よく聞きます。
アクセスは月10,000。でも、リードは月2〜3件。営業が別で頑張ってやっとその状態。
多くの企業が「SEO記事」を「アクセス装置」だと思っているから、こういう結果になります。
でも、本来、SEO記事は「営業装置」であるべきです。

この記事で理解できること
✅ SEO記事が商談につながらない本当の理由
✅ 「情報分岐設計」とは何か
✅ 1本の記事で4つの役割を同時に果たす方法
✅ 営業導線を記事に組み込むテクニック
✅ もじの木が「速いのに営業力がある」理由
「ただ書く記事」と「営業する記事」の決定的な違い
多くの企業がSEO記事に期待していることは「アクセスを集めること」です。
だから、SEO記事の目的も「上位表示」になります。

ありがちなSEO記事
検索 → 記事にアクセス → 情報を読む → 離脱
📊 成果:PV数は多い。でも商談は発生しない。
営業装置になるSEO記事
検索 → 記事にアクセス → 課題に気づく → 信頼する → 資料DL → 相談 → 商談
📊 成果:PVは少なくてもいい。リードと商談を生む。
同じ「記事」なのに、なぜこんなに違うのか。
答えは「情報設計」です。

情報設計?つまり「どう書くか」ってこと?
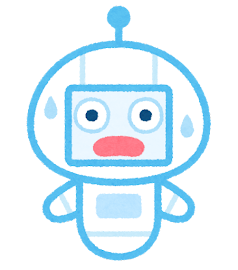
そっや!どこで読者の気持ちを変えるか、がぜんぜん違うんや!
「情報分岐設計」とは:1本の記事に4つの役割を組み込む

「情報分岐設計」=1本の記事の中に、読者の心理段階に合わせて「4つの異なる役割」を組み込む戦略です。
分岐①:集客(A層)「検索意図を満たす」
役割:記事に誘う
検索ユーザーが「何を求めて検索したのか」をまず満たします。
タイトル、冒頭、見出しで「あ、これ私の悩みだ」と感じさせる。これが第一段階。
分岐②:教育(B層)「思想・課題の自覚を促す」
役割:読者の思考を変える
「実は、あなたの考え方が間違ってるかもしれない」と気付かせる。
「SEO記事=アクセス装置」ではなく「営業装置」という新しい視点を与える。
分岐③:信頼(C層)「実績・一次情報で納得させる」
役割:相手を信じさせる
「あ、でも本当に可能なの?」という疑問が出てきます。ここで「実績」「事例」「データ」を見せる。
分岐④:商談(D層)「行動を促す」
役割:次のアクションに導く
最後に「でも、自分たちでできるのかな…」という不安を解消して、アクションを促します。
よくある失敗:分岐がない記事
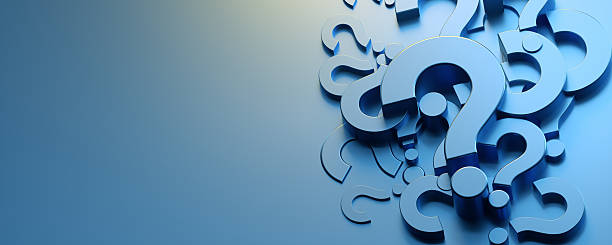
情報分岐設計の型:「温める→信頼→アクション」の流れ

CTAの「段階的な強さ」:1記事で3段階の提案

重要なのは、最初から「商談しましょう」と強く言わないことです。
軽いCTA(B層~C層向け)
「このアプローチについて、もっと詳しい資料を用意しました。ダウンロードしませんか?」
→ 心理的ハードルが低い。まずはここから。
中間CTA(C層向け)
「実際に企業がこの設計で成功した事例3つを、別記事で紹介しています。見てみませんか?」
→ より具体的な例で、さらに確信を深める。
強いCTA(C層~D層向け)
「あなたの企業で、この設計がどう機能するか、まずは1本で試してみませんか?無料相談も可能です。」
→ ここまで来たら、心は決まってる。最後のひと押し。
成果の差:「従来型」vs「分岐設計型」
| 項目 | 従来型SEO記事 | 分岐設計型記事 |
|---|---|---|
| 目的 | 上位表示 | 商談獲得 |
| ユーザーの流れ | 検索→読む→離脱 | 検索→課題認識→信頼→行動 |
| 月間PV | 20,000 | 3,000 |
| 月間リード | 1~2件 | 8~12件 |
| CTA配置 | 1箇所(最後) | 3段階(軽い→中→強) |
| 1記事のROI | 低い | 高い |
「PVは少なくてもいい。リードと商談を生む」という転換点が、ここにあります。

えっ、PVが6分の1に減ってるのに、リードが6倍以上に増えてる…!?
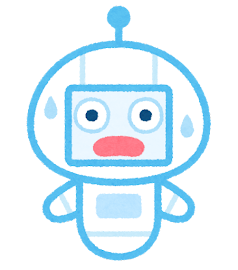
そうや!設計が違うと、「見られる記事」から「売れる記事」に変わるんや!
企業にとってのメリット:SEOを「営業資産」に変える

もじの木だからできること:「速さ」と「営業力」の両立
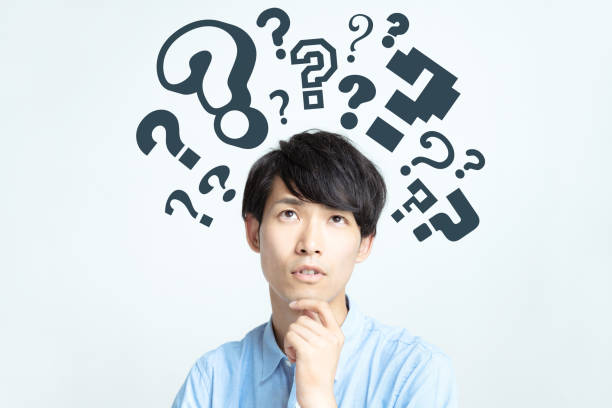
「情報分岐設計」は最高ですが、普通に実装すると時間がかかります。
戦略ミーティング(1回目)→ 営業部門とヒアリング(2回目)→ 構成を練り直す → CTAを最適化する…これで2~3週間。
でも、もじの木は違う。
結論:「情報設計力」こそが、記事の価値を決める
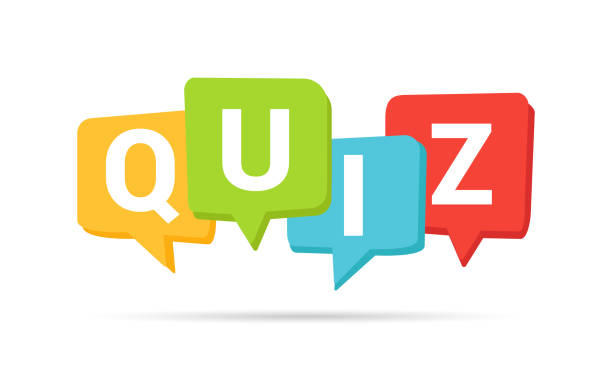
「良い文章=売れる記事」ではありません。
売れる記事=「読者の心理段階に合わせて、4つの役割を正確に果たす」記事です。
集客 → 教育 → 信頼 → 商談
この流れが1本の記事の中に設計されていれば、PVが少なくても、リードと商談を生み続けます。
そして、この4層の分岐設計を「型」として組み込んだから、もじの木は「速く」「営業力のある」記事を出し続けることができるんです。
「ただのSEO記事」と「営業装置記事」の差を、まずは1本で体験してみませんか?
1本の記事から、営業導線を持つオーガニック集客が生まれる体験をしてください。その先に見える「成果を生むSEO」の形が、必ず見えてきます。
SEO記事制作を外注するなら「もじの木」
リサーチ・構成・執筆・装飾・WordPress入稿まですべてワンストップ対応。
7,000文字の記事を最短1営業日(通常3営業日)で納品。
文字単価1.5円で、高速×高品質なSEO記事を実現しています。
今なら初回限定で、7,000文字相当1本を無料で執筆。
「まずはクオリティを見てから依頼したい」という方に最適です。