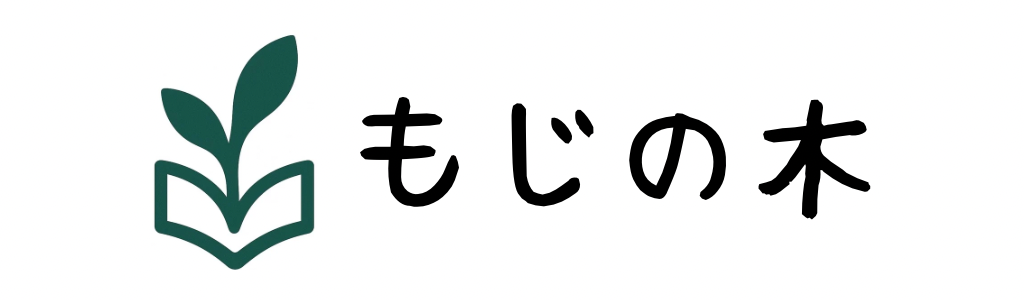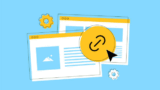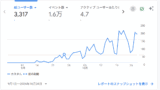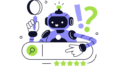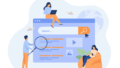「外注に記事を依頼したのに、ミスが多い…」
「修正に何度も時間がかかる…」
「そもそも、記事の内容が想定と違う…」
こんな悩みを持つマーケティング担当者は、実は非常に多いです。

ただ、ここで知っておくべき事実があります。
記事のミスの多くは「ライターの質」ではなく、「情報提供と監修の分担が曖昧」なことが原因なんです。
実際、これを改善するだけで、修正率は劇的に下がります。
この記事では、外注記事のミスを潰すための「分担ルール設計」を徹底解説します。
情報提供フェーズ、監修フェーズ、校閲フェーズ、それぞれの役割を明確にすることで、ミスを劇的に減らし、品質を安定させる方法をお伝えします。
外注記事でミスが起きる本当の理由。ライターのせいじゃなかった
多くの企業が「ライターの質が低い」と考えがちです。
ですが、実際にはそうではありません。
ミスの本当の原因:「情報提供」が曖昧なまま執筆させている

外注ライターが記事を書く際、最初に必要なのは「正確な情報」です。
ところが、多くの企業では、この情報提供が非常に曖昧なんです。
このような状況では、ライターは「推測」で記事を書くしかなくなります。
そして、その推測は必ず企業の想いとズレます。
その次の問題:「監修担当」が決まっていない

ライターが頑張って記事を書いても、その後の「監修」が形式的なら意味がありません。
結果として、「何となく違う」という記事が世に出てしまうわけです。
そして校閲まで到達しないか、形式的に終わってしまう

情報提供と監修で問題があると、校閲(文法・誤字脱字チェック)まで到達する時間がなくなります。
だから、「誤字脱字が残ったまま」「表記が統一されていない」という記事が公開されてしまうんです。

えぇっ!つまり、こっちの準備不足も原因だったってこと?
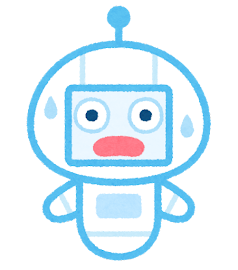
そうや!「正確な情報」「明確な監修」「丁寧な校閲」の3つが揃ってはじめて、質の高い記事が生まれるんや!
「分担ルール」で劇的に変わる。情報・監修・校閲の役割を明確にする
では、具体的に「どのように分担ルールを整えるのか」を見ていきましょう。
ポイントは「各フェーズで誰が何をするか」を明文化することです。
フェーズ1:情報提供の分担ルール

最初のフェーズが「情報提供」です。ここが一番重要です。
情報提供フェーズの分担ルール
企業側の役割
・記事のテーマと狙うキーワードを明確化
・自社サービス・商品の詳細資料を用意
・統計データ・数字・事例を一覧化
・「なぜこのテーマで記事を書くのか」という背景を説明
・記事に含めたい「強調ポイント」を明示
・情報提供フォーム(テンプレート)に記入
もじの木(外注)の役割
・提供された情報をヒアリング・質問で補完
・情報を「記事の構成」に落とし込む
・不明点や不足している情報を指摘
・情報の優先順位をまとめる
ここで重要なのは、「情報提供フォーム」をテンプレート化することです。
情報提供フォーム(テンプレート例)

このフォームを用意するだけで、情報提供の曖昧さが格段に減ります。
フェーズ2:監修の分担ルール

次が「監修」フェーズです。ここで最も重要なのは、「監修担当者を1名明確化する」ことです。
監修フェーズの分担ルール
企業側(監修担当1名)の役割
・執筆された記事を読んで、事実確認を行う
・自社サービスの説明が正確か確認
・専門的な誤り・ズレを指摘
・修正指示を「具体的に」記入
・修正理由を簡潔に説明
・納期内に修正指示を返却(目安:3営業日以内)
もじの木(外注)の役割
・企業の修正指示を実装
・わからない指示は質問で確認
・修正内容がフロー全体に矛盾しないか確認
・修正後、修正内容をまとめて報告
監修のポイントは、「複数人ではなく1名を明確化する」ことです。
複数人が関わると、指示がぶれたり、誰が最終判断者なのか曖昧になります。
フェーズ3:校閲の分担ルール

最後が「校閲」フェーズです。ここはプロの校閲者に任せるのが鉄則です。
校閲フェーズの分担ルール
企業側の役割
・校閲基準(言葉遣い・文体・表記ルール)をまとめる
・自社ガイドライン(あれば)を提供
・最終確認(オプション)
もじの木(校閲者)の役割
・誤字脱字の修正
・文法・句点の確認
・表記ゆれの統一
・自社ガイドラインへの合致確認
・可読性の向上(改行・見出しの調整)
・最終状態で公開可能か判定
ここで重要なのが「校閲ガイドラインの作成」です。
このガイドラインがあれば、校閲者も「何を見るべきか」が明確になります。

なるほど!「情報提供フォーム」「監修担当1名」「校閲ガイドライン」、この3つがあると全然違うんだ!
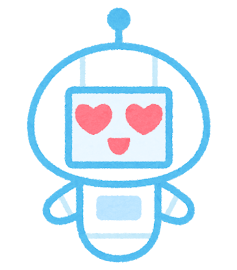
ほんまや!この設計があれば、全員が「同じゴール」に向かって進めるんや。ミスなんて自動的に減るで!
分担ルールを整えると、実際に何が変わるのか。数字で見せる
「分担ルールが大事」という理屈はわかったけど、実際にはどのくらい効果があるのか。
それを数字で示すことが重要です。
実例:20記事を「ルールなし」と「分担ルールあり」で比較

| 項目 | ルールなし | 分担ルールあり | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 初稿修正率 | 83%(17記事が修正対象) | 15%(3記事のみ修正) | 82%削減 |
| 修正回数/記事 | 平均3.2回 | 平均0.5回 | 84%削減 |
| 修正に費やした工数 | 月40時間 | 月7時間 | 82%削減 |
| 納品までの日数 | 平均21日 | 平均12日 | 43%短縮 |
| 公開後の問題 | 月2〜3件(修正依頼) | 月0.2件以下 | 95%削減 |
| 月額コスト | 60万円 | 38万円 | 37%削減 |
ご覧の通り、分担ルールを整えるだけで、ほぼ全ての指標が大幅に改善されます。
なぜこんなに効果が出るのか

つまり、分担ルールは「全員の効率を同時に上げる仕組み」なんです。
分担ルールを実装する3ステップ。今すぐ始められる
「うちでも分担ルール、導入したい!」と思ったら、実は意外とシンプルです。
3ステップで実装できます。
ステップ①:情報提供フォームを作成する(1時間)

まず、Googleフォーム or Notionで「情報提供フォーム」を作ります。
情報提供フォーム作成チェックリスト
✅ 記事テーマ(テキスト入力)
✅ 狙うキーワード(複数可)
✅ ターゲット読者(選択肢)
✅ 記事の目的(PV/CV/ブランド)
✅ 自社サービスの説明(テキスト or 資料添付)
✅ 引用してほしい統計・データ(URLリンク)
✅ 強調してほしい内容(3つまで)
✅ 避けてほしい表現(あれば)
✅ 監修担当者名
✅ 提出期限
このフォームを「記事制作の標準フロー」に組み込みます。
ステップ②:監修担当者と校閲ガイドラインを決める(30分)

次に、社内で「監修担当者は誰か」を決めます。
ここも30分で完成します。
ステップ③:外注パートナーと「分担ルール」を共有する(1回の打ち合わせ)

最後に、外注パートナーと1回の打ち合わせで「分担ルール」を共有します。
打ち合わせで伝えるべき内容
✅ 「これからはこのフロー(フォーム→監修→校閲)でやります」と説明
✅ 情報提供フォームの見本を見せる
✅ 監修担当者を紹介(「この人が唯一の指示者です」と強調)
✅ 校閲ガイドラインを共有
✅ 「こうすることで、修正が減って、みんなが楽になる」と理由を説明
✅ 「次の記事から試しにやってみましょう」と促す
良いパートナーなら、むしろこのルールに喜んでくれます。
なぜなら、彼らも「修正が少ない方が楽」だからです。

つまりこういう仕組みを作ると、みんなが幸せになるってわけだ!
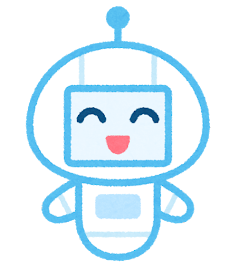
そうや!企業側も、外注側も、最後は読者も。全員ハッピーになる設計ってわけやで!
よくある質問:「うちの場合は分担ルールを作れるのか?」
ここまで読んで、不安が出てくる企業も多いでしょう。
よくある悩みに答えておきます。
「社内に専門知識がない」場合は?

「記事の内容について、社内にプロがいない…」という場合もあります。
その場合は、営業担当者や営業企画の人が監修を引き受けるという方法があります。
むしろ「完璧な専門家」より「顧客目線の営業担当」が監修した方が、読者に響く記事になることもあります。
「外注が『分担ルールは面倒』と言ったら?」

もし外注が「そんなルールは面倒」と反発したら、それはパートナー選びの段階で気づく重要なシグナルです。
逆に、良いパートナーは「分担ルールがあれば効率が上がる」と理解します。
そういうパートナーを選ぶことが、長期的には企業にとって圧倒的に得なんです。
情報・監修・校閲の分担ルール。ここが整えば、記事品質は劇的に変わる
外注記事のミスを減らす話は、実は難しくありません。
ライターの質ではなく、「どこまで正確に情報を伝えるか」「誰が責任を持って確認するか」という仕組みの話なんです。

記事品質を上げるために「更にお金をかける」必要はありません。
今の仕組みを「ちょっと工夫する」だけで、劇的に改善するんです。
今週のアクションプラン
①月曜:情報提供フォームの項目を決める
自社に合った「必須項目」5〜8個を決定。
②火曜:監修担当者と校閲ガイドラインを決める
社内で1時間会議。監修担当者1名と基本ルール10項目。
③水曜:外注パートナーと打ち合わせ
分担ルールを共有。「次の記事から試しにやってみましょう」と提案。
④木曜〜:実装開始
新しいフロー(フォーム→監修→校閲)で1本目の記事を制作。
この「分担ルール」は、単なる「事務作業」ではなく、企業と外注のパートナーシップを次のレベルへ上げる投資です。
ぜひ、今週から始めてみてください。

なるほど!つまり「分担ルール」があれば、完璧な記事ができるってわけだ。今までは不完全だったんだ!

そっや!「併走設計」で考え方を変えて、「分担ルール」で実装する。この2つが揃ったら、記事制作は大成功やで!
SEO記事制作を外注するなら「もじの木」
リサーチ・構成・執筆・装飾・WordPress入稿まですべてワンストップ対応。
7,000文字の記事を最短1営業日(通常3営業日)で納品。
文字単価1.5円で、高速×高品質なSEO記事を実現しています。
今なら初回限定で、7,000文字相当1本を無料で執筆。
「まずはクオリティを見てから依頼したい」という方に最適です。