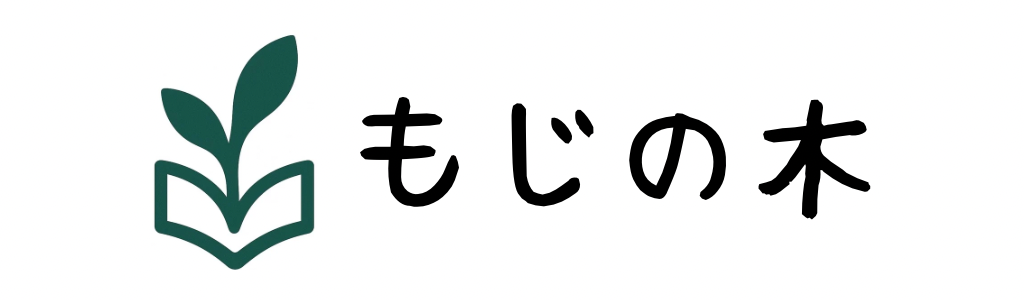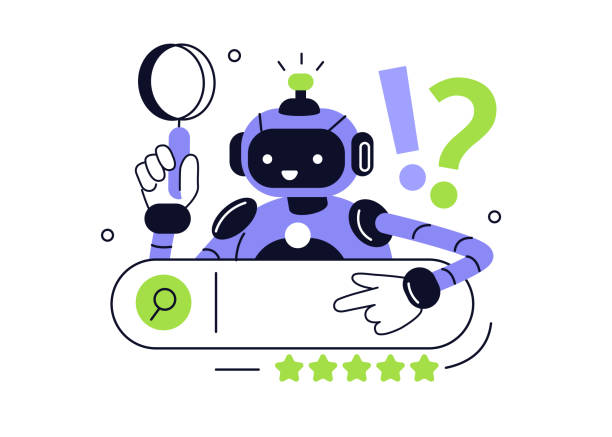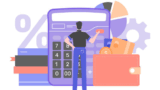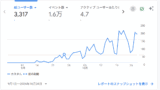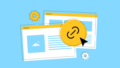「記事制作をすべて外注すると、コストが月額50万円を超えてしまう…」
「全部自社でやろうと思ったら、担当者が疲弊して3ヶ月で挫折した…」
「結局、中途半端な体制で、成果も安定しない…」
こんな悩みを抱えているマーケティング担当者の声は、私たちの元に毎日のように届きます。

実は、この矛盾は「内製か外注か、どちらかに決めよう」という二択の発想から生まれているんです。
成功している企業は、その両方を戦略的に組み合わせる「併走設計」を採用しています。
この記事では、内製と外注の最適な組み合わせ方を徹底解説します。
丸投げ外注の失敗、全内製の工数爆発から抜け出し、最小工数で最大成果を実現する「併走設計」の方法論と実装ステップ、そして実例をお伝えします。
「丸投げ外注」と「全内製」のどちらもが失敗する理由
多くの企業が陥る落とし穴は、二者択一の判断にあります。
実際のところ、どちらの選択も「最大成果」には遠いんです。
「全外注」で失敗する企業の共通点

記事制作をすべて外注に丸投げすると、一見すると「工数が減った」ように見えます。
しかし現実は違います。
つまり、工数は減っても、実質的には修正に時間がかかり、結果的に総工数は減らないという矛盾が生じるんです。
「全内製」で失敗する企業の共通点

一方、「記事制作は全部社内でやろう」と決めた企業も同じくらい失敗します。
理由はシンプル。企画・執筆・装飾・SEO対策・分析…これすべてを社内でやることは、工数が物理的に成立しないからです。
多くの企業が「最初は全内製でやろう」と決めても、3ヶ月で外注に切り替わるのはこのためです。
結果:どちらを選んでも「成果が最大化されない」
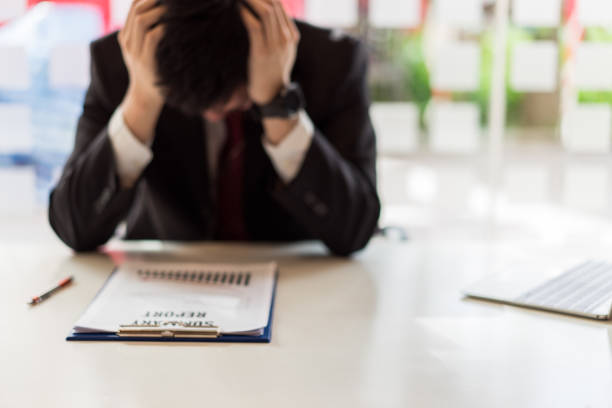
| 選択肢 | 月間工数 | 月額費用 | 品質安定性 | 成果の再現性 |
|---|---|---|---|---|
| 全外注 | 修正で30〜40時間 | 45万円〜 | 低い(修正ループ) | 安定しない |
| 全内製 | 80時間以上 | 0円(給与費用) | 低い(ノウハウ不足) | 属人化 |
| 併走設計 | 10〜15時間 | 30万円程度 | 高い(仕組み化) | 再現性あり |
見てわかる通り、成功している企業は第3の選択肢「併走設計」を採用しているんです。

なるほど!外注も内製も、どちらも極端だから失敗するのね。中間地点を狙うってわけだ!
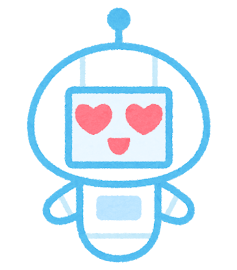
そうや!「併走設計」は、社内リソースを活かしつつ、プロの工数削減を組み合わせる戦略なんや。ここからが本番やで!
「併走設計」とは何か。役割分担で最小工数×最大成果を実現する
では、具体的に「併走設計」とは何なのか。
シンプルに言うと、企業の「得意な部分」と外注の「得意な部分」を戦略的に分け、その境界線を明確にすることです。
併走設計の基本構造:社内と外注の役割分担

併走設計での役割分担(標準モデル)
社内が担当する部分(得意=ビジネス理解)
・トピック選定と企画立案
・ターゲット顧客の定義
・自社サービス・商品の一次情報提供
・最終チェック&承認
・成果測定とKPI追跡
外注が担当する部分(得意=執筆・構成・装飾)
・記事構成の設計
・SEO最適化の実装
・執筆(ライティング)
・ビジュアル装飾とレイアウト
・初期チェック&修正提案
このように「社内にしかできない部分」と「外注にやらせるべき部分」を明確に分けることで、各々のリソースが最適に配分されるわけです。
併走設計で工数が減り、成果が安定する理由

つまり、併走設計は「工数削減×品質向上×コスト最適化」の三角形を同時に成立させるんです。
丸投げ外注との違いを明確に。併走設計で何が変わるのか
「結局、外注でしょ?何が違うの?」という質問をよく受けます。
この誤解を解くために、丸投げ外注と併走設計の違いを数字で示すことが重要です。
実例:10記事を丸投げ外注 vs 併走設計した場合の比較

| 項目 | 丸投げ外注 | 併走設計 | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| 社内工数 | 25時間 (修正・確認) | 7時間 (企画・確認) | 72%削減 |
| 月額費用 | 45万円 (記事単価4.5万) | 30万円 (記事単価3万) | 33%削減 |
| 修正回数 | 平均3回 | 平均0.5回 | 83%削減 |
| 納期 | 4週間 | 2.5週間 | 40%短縮 |
| 品質 | ライター依存 (不安定) | 社内チェック (安定的) | 再現性確保 |
| トータル時間 | 35時間 | 12時間 | 66%削減 |
ご覧の通り、併走設計では社内工数が72%削減されながら、単価も33%下げられ、かつ品質が安定するという、全ての指標で優れた結果になっています。
なぜ併走設計は「安い×高品質×早い」を実現できるのか

つまり、併走設計は「社内と外注が同じ目標を向いている状態」なので、全員の効率が上がるわけです。

えぇっ!72%も工数削減できて、さらに単価も安くなるの?そんなことあるの!?
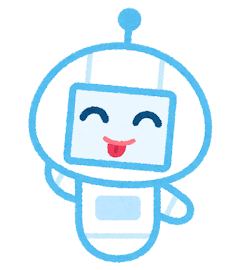
ほんまやで!設計がしっかりしてたら、全員が無駄な工数を減らせるんや。修正なしで一発OK、こんな状態が実現するってわけやで!
併走設計を実装する3ステップ。今日から始められる具体的な方法
「併走設計、うちもやってみたい」と思うのは自然な流れです。
でも「難しそう…」と感じている方も多いはず。
実は、併走設計の実装は、シンプルな3ステップで始められます。
ステップ①:役割分担設計(社内と外注の「線引き」を決める)

まず最初に、社内チーム内で「誰が何を担当するか」を明確にします。
役割分担設計のチェックリスト
✅ 企画担当:誰がトピック選定・顧客定義をするか
✅ 情報担当:自社情報を整理・提供する人
✅ チェック担当:記事の最終確認・承認を誰が行うか
✅ 分析担当:成果測定(PV・CVなど)を誰が追跡するか
✅ 指示出し担当:外注への依頼・修正依頼の窓口は誰か
この時点で重要なのは、「複数の人が携わるのではなく、各タスクの『主責任者』を決める」ことです。
そうしないと、また「指示がぶれる→修正が増える」という悪循環に陥ります。
ステップ②:KPI設計&運用フロー整備(成果の測り方と進め方を決める)

次に、「この記事で何を達成したいのか」をKPI(重要指標)として定義します。
このKPIを決めることで、外注への依頼も「何を重視するのか」が明確になります。
例えば「月間PV1000を目指す」なら、SEO対策を重視した記事設計になります。「CV10を目指す」なら、営業寄りの構成になります。
ステップ③:外注パートナーとの「併走ルール」を定める

最後に、外注との「進め方のルール」を決めます。
併走ルールで定めるべきこと
✅ 企画段階での打ち合わせ方法(何回、いつ)
✅ 情報提供のタイミング(何までに、どの形式で)
✅ 構成案の確認プロセス(社内チェック→修正→確定の流れ)
✅ 修正依頼の基準(どのレベルなら修正対象か)
✅ 納期の目安(企画決定から納品まで何日か)
✅ 報告・分析の頻度(月1回のミーティングなど)
このルールがあると、外注側も「このクライアントとの進め方」を理解するため、スムーズに進みます。
よくある悩み。「うちの場合、併走設計はできる?」という不安への答え
ここまで読んで、「いや、うちの場合は…」という不安が浮かぶ方も多いでしょう。
よくある悩みに、先に答えておきます。
「社内リソースが本当にない」場合はどうする?

「気持ちはわかるけど、うちは本当に人手がない…」という声もあります。
その場合、最小限の役割分担から始めるというアプローチがあります。
大切なのは「完璧な併走設計」ではなく、「今の自分たちができる範囲で、修正ループを減らす工夫をする」という意識です。
「外注相手が、社内の事情を理解してくれない」場合は?

「外注に指示を出しても、こちらの意図が伝わらない…」という悩みもあります。
これは、実は「相手のせい」ではなく、「指示の伝え方」の問題です。
実は、良い外注パートナーを探すのではなく、「こちらが明確な指示を出す」という工夫が最も重要なんです。

こっちの指示の出し方が何より大切だったってわけだ!
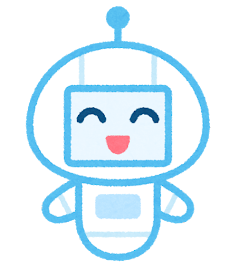
そうや!良いパートナーシップて、相手が優秀なんじゃなくて、互いに「何を求めてるのか」を理解してるのが大事やで!
内製と外注の併走設計。最小工数で最大成果を実現する戦略まとめ
「丸投げ外注」と「全内製」の両極端から抜け出し、最適なバランスを見つけることが、記事制作の成功には不可欠です。
併走設計は、単なる「外注の活用法」ではなく、企業の体制を次のレベルへ引き上げるパートナーシップ戦略なんです。

記事制作の体制は、ビジネス成長の土台です。
「安いだけの外注」や「工数ばかりかかる内製」に満足していては、ライバル企業に差をつけられます。
今こそ、「併走設計」という第3の道を選ぶ時です。
次のアクションプラン
①今週中に、現在の記事制作の課題を整理する
修正が多い? 工数が多い? コストが高い? 品質がばらつく? 今の問題を言語化することが、改善の第一歩。
②社内チーム(3〜4名)で「役割分担」を相談する
企画・情報提供・チェック・分析、各タスクの主責任者を決める。1時間の会議で決まります。
③KPIを数字で定義する
「PV目標」「CV目標」「掲載順位」など、今期達成したい成果を決める。
④外注パートナーと「併走ルール」を相談する
今の外注がいるなら、体制改善について相談してみてください。良いパートナーなら、一緒に工夫してくれます。
併走設計の導入は、単なる「外注との付き合い方」ではなく、企業全体のコンテンツ戦略を次のレベルへ押し上げる決断です。
ぜひ、今日から始めてみてください。
SEO記事制作を外注するなら「もじの木」
リサーチ・構成・執筆・装飾・WordPress入稿まですべてワンストップ対応。
7,000文字の記事を最短1営業日(通常3営業日)で納品。
文字単価1.5円で、高速×高品質なSEO記事を実現しています。
今なら初回限定で、7,000文字相当1本を無料で執筆。
「まずはクオリティを見てから依頼したい」という方に最適です。